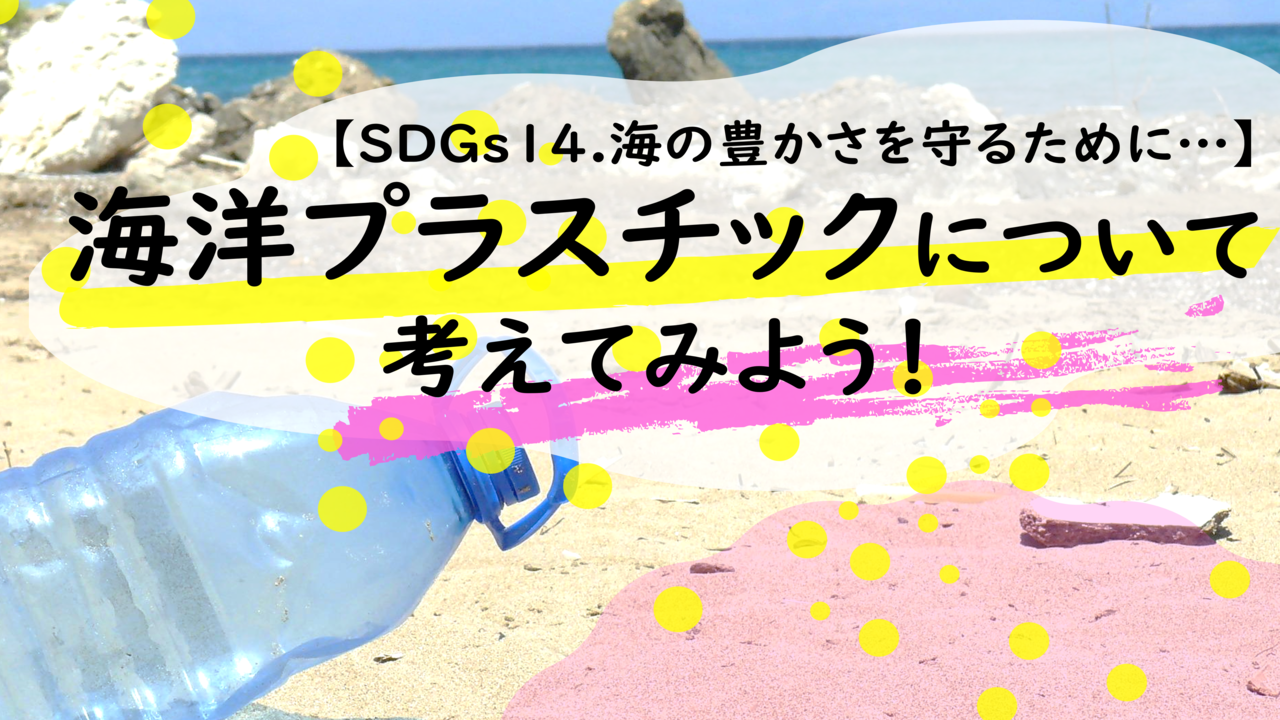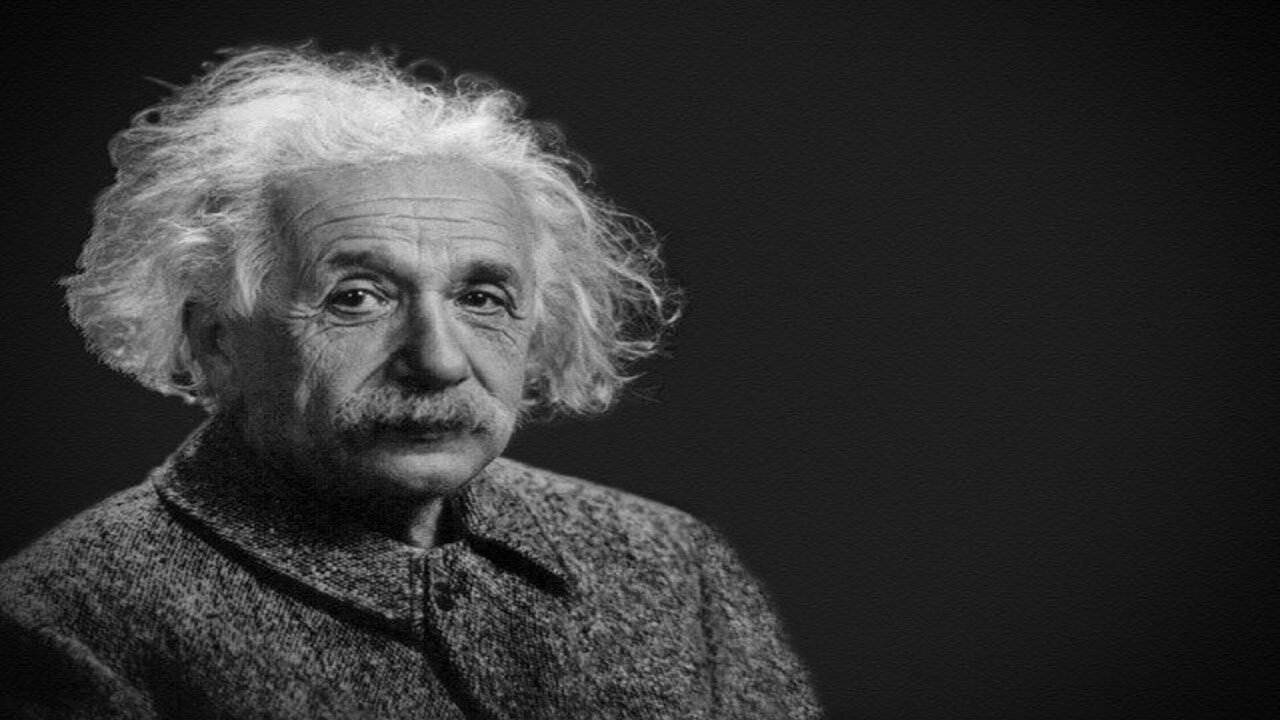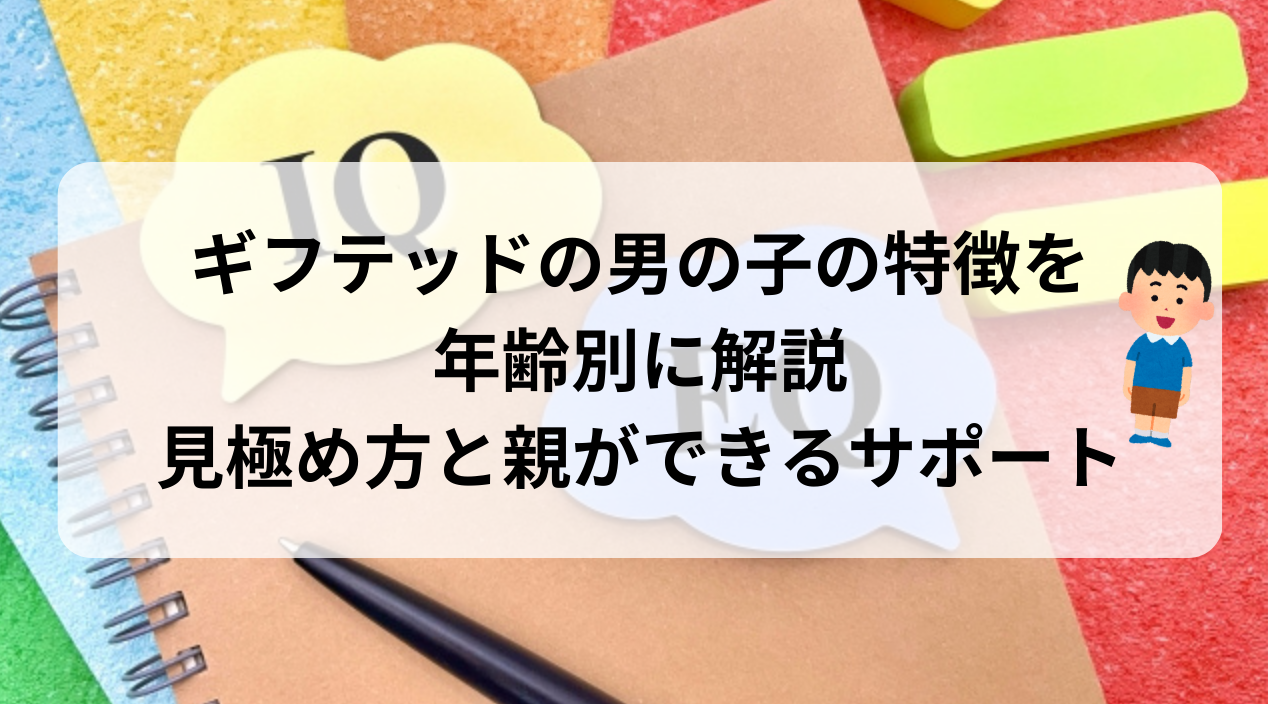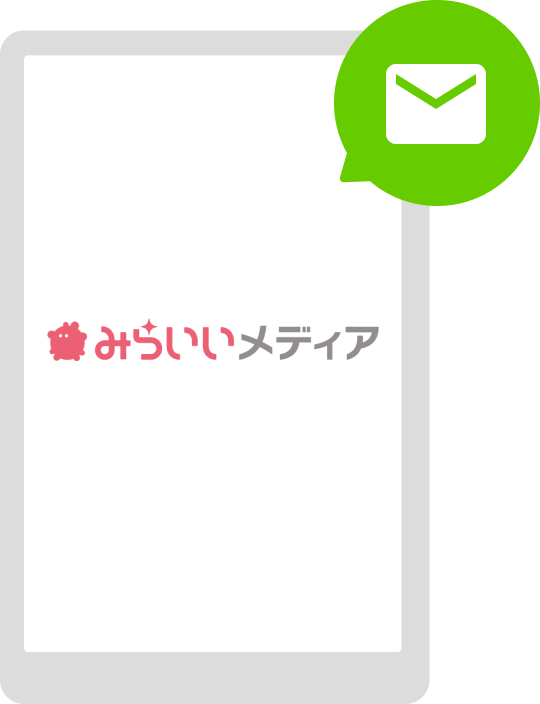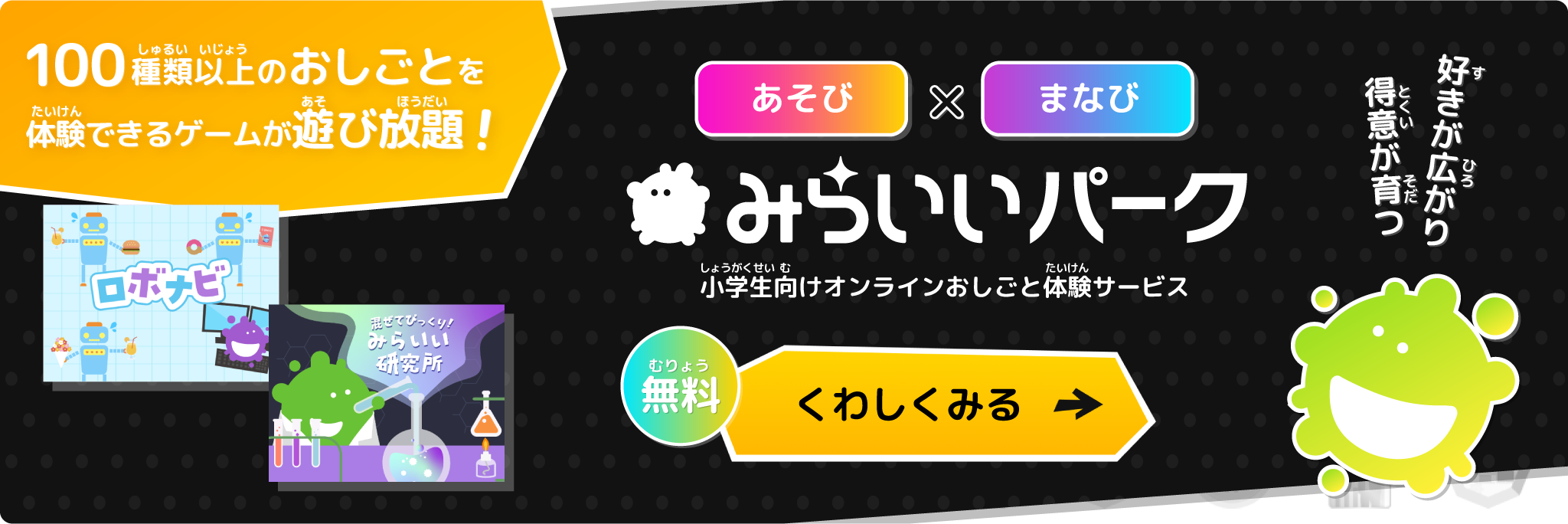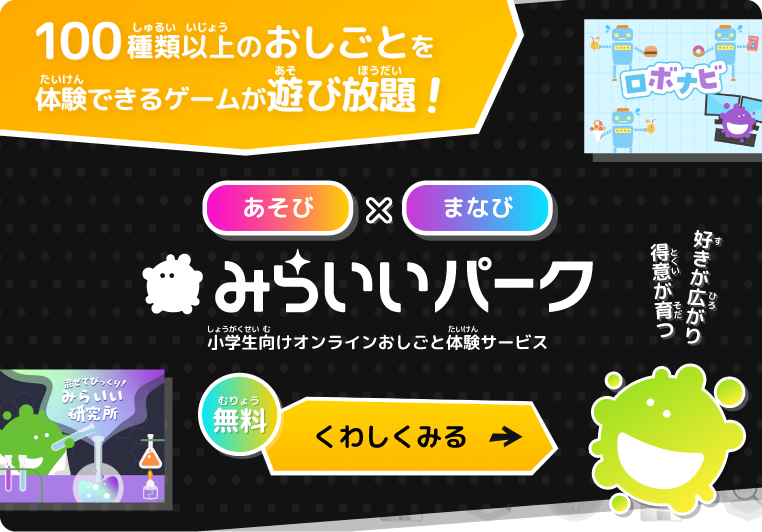円安と円高って何?小学生向けに分かりやすく解説!
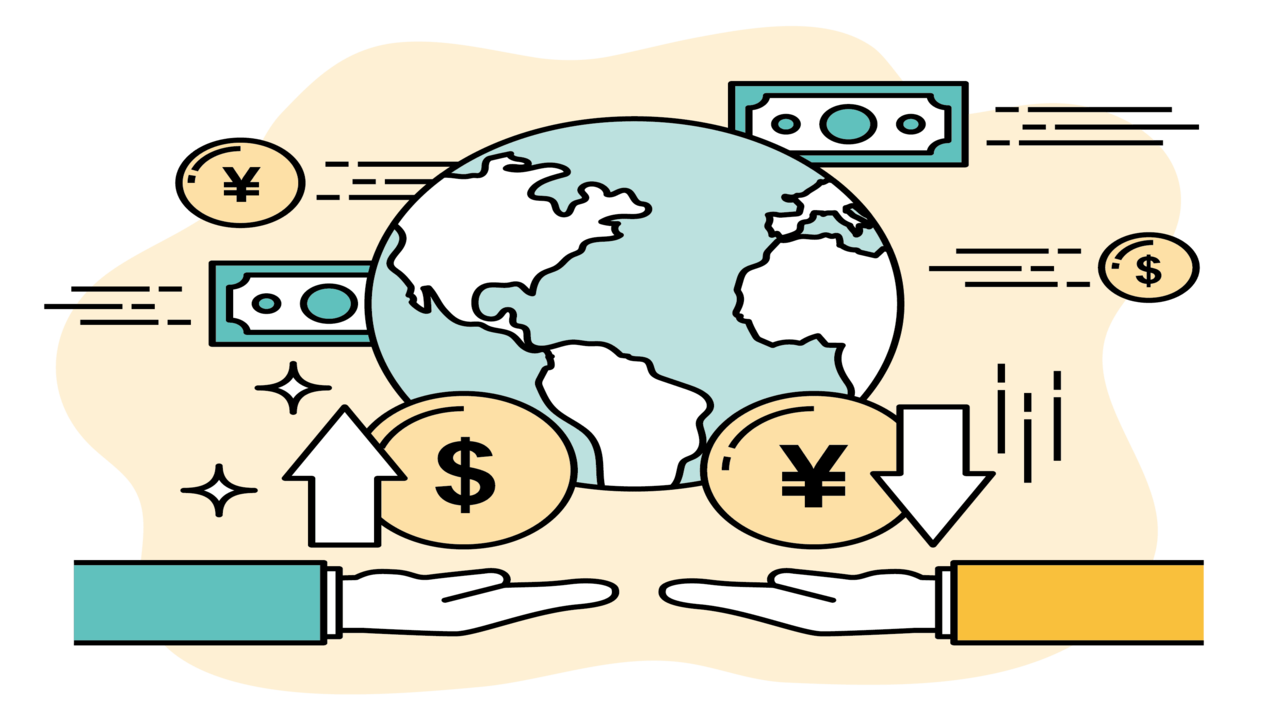
テレビやニュースでよく聞く「円安」や「円高」という言葉。子どもに「円安って何?」と聞かれると、ちょっと説明が難しいですよね。この記事では、「円安」「円高」とは何か、どういうところで使われる言葉なのか、そして私たちの生活にどう影響するのかを、小学生にもわかりやすく解説していきます。
円安と円高の基本的な意味
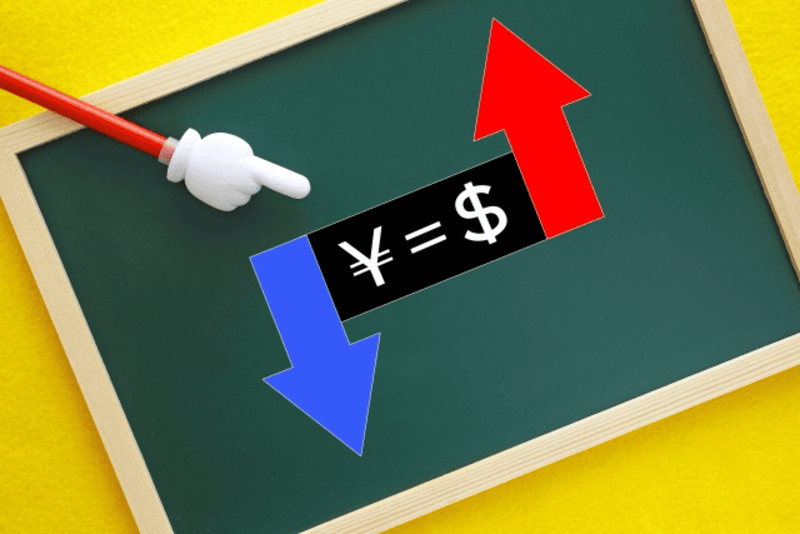
「円安(えんやす)」と「円高(えんだか)」は、日本のお金(円)が、外国のお金に対してどれくらいの価値があるかを表す言葉です。
たとえば、ある時点で1ドルが100円だったとしましょう。
それが、なんらかの影響を受けて1ドルの値段が変わります。
- 1ドル=90円 になった場合→円高(円の価値が上がった)
- 1ドル=110円 になった場合→円安(円の価値が下がった)
つまり、「円高」になると同じお金でより多くのドルが買える、「円安」になると同じお金で少ないドルしか買えなくなるということです。具体的な数字でみてみましょう。
あなたは1000円持っています。それをドルに変えるとします。
1ドル90円の時に、1000円出せば、11ドル買うことができます。
しかし、1ドルが110円になると、1000円出しても、9ドルしか買えません。
こういった状態のことをそれぞれ円高、円安といいます。
円の価値が高いか安いかで考える
1ドル〇〇円という表示のされ方だと、数字が大きくなるのに「円安」というのは混乱しますよね。数字が大きくなるにもかかわらず、言葉は「安(やす)」となるための混乱ではないでしょうか。その際は、価値がどうなるのかという言葉を入れて考えるようにしてみましょう。
- 円高=円(の価値が)高い
- 円高=円(の価値が)安い
このようにいきなり数字で考えるのではなく、言葉で整理してから金額のことを考えると、理解しやすくなります。
また、ここも難しいポイントなのですが、いくらなら円高なのか、いくらなら円安なのかは決まっていません。報道されている情報は、あくまでも「これまでに比べて」円高なのか円安なのかです。
たとえば、2012年には1ドル70〜80円台でしたが、2015年には1ドル125円となり、当時はかなりの円安だと報道されました。
2025年現在はどうでしょうか?1ドル150円となっている時期がありましたね。2025年の価値で考えると、125円は「円高」だと考えられますが、2012年時点では「円安」だったのです。このように、円高、円安でさえもその後のお金の動きで変わることがあります。
円安・円高はお金の交換場所で使われる言葉

世界ではさまざまな種類のお金が使われています。
- 日本では「円(JPY)」
- アメリカでは「ドル(USD)」
- ヨーロッパの多くの国では「ユーロ(EUR)」
- 中国では「元(CNY)」
- イギリスでは「ポンド(GBP)」
- 韓国では「ウォン(KRW)」
お金の種類だけでなく、その価値も国ごとに変わるため、円とドル、円とユーロなどお金同士の交換が必要です。
お金の価値も為替レートも日々変わっている
このように、異なる国のお金を交換する時の金額のことを「為替(かわせ)レート」といいます。為替レートは、毎日変わっています。日本で起きたことだけでなく、世界中の投資家や企業、政府の動きによっても変動するため、経済ニュースなどで「今日の円相場」といった情報が頻繁に伝えられるのです。
円安と円高が起こる仕組み

円安や円高はなぜ起こるのでしょうか?続いては、その仕組みを解説していきます。
円安や円高は、外国為替市場(がいこくかわせしじょう)という場所で、お金が売られたり買われたりすることで決まります。
円に価値があると思う人が多くいれば、円高になり、円に価値があると思う人がが少ない場合は円安になります。
難しい言葉でいうと、需要(じゅよう)と供給(きょうきゅう)によって円高になるのか円安になるのかが変わってきます。
- 需要(じゅよう):モノやお金を欲しいと考えている人がどれくらいいるか
- 供給(きょうきゅう):モノやお金を欲しい人にどれだけ渡せるか
最初からお金で考えると、少し想像しづらいかもしれません。
その際は、生産される数が少ないおもちゃなどで考えてみると良いでしょう。
10人の人が欲しいと思っているおもちゃが1個しか作られなかった場合、その1つのおもちゃはみんなが欲しいと考えているため、価値は高くなりそうです。
そして、その価値が反映されておもちゃの値段も高くなることが予想されますね。
為替レートが変わるように、お金の価値は変わっていくため、お金の金額とお金の価値がいつでも同じではないことも理解しておく必要があります。
それでは、お金に戻して円高と円安が起こる状況について考えてみましょう。
- 日本の景気が良くなると、外国の人たちが円を欲しがる → 円高
- 日本の景気が悪くなると、円を売る人が増える → 円安
- 世界の経済が不安定になると、安全と考えられる円が買われる → 円高
ほかにも、金利の変化(日本の金利が高くなると円高、低くなると円安)や、貿易の影響(輸出が多いと円高、輸入が多いと円安)も影響します。戦争や自然災害などが起こると、お金の価値が変わることもあります。
円安と円高が私たちに与える影響

これまで、国の間で行われることとして円高と円安を解説しました。ここからは私たちの生活にどのように関わってくるのかを解説します。小学生のお子さまに直接影響が出ることは少ないでしょう。しかし、商品の価格などを観察してみると、身近なところに影響があるのを発見できるかもしれません。
輸入品の価格
輸入や輸出は、国を超えてモノが動きます。日本はガソリンやたくさんの種類の食べ物を輸入しています。そのため、円高や円安の影響を大きく受けます。
1ドル90円(円高)の場合、10,000円で約111ドル分のモノを買うことができます。一方で、1ドル120円(円安)の場合、10,000円を出しても83ドル分のモノしか買うことができません。そのため、円高の場合には、海外からの輸入品が安くなり、円安の場合、輸入品が高くなるのです。ガソリンスタンドに行く場合、値段を観察したり、これまでの値段を調べたりしてみると、円高や円安の影響を受けていることがわかりやすいです。
家族旅行旅行や留学への影響
家族旅行や留学にも影響が出ます。現地で観光をしたり、生活をするにはお金がかかってくるからです。ここでは、円を100ドルに交換すると考えてみましょう。
その時の為替レートが、1ドル100円の場合、10,000円で100ドルを手に入れることができます。
一方で、1ドル120円の時には12000円出さなければ、100ドルを手に入れることができません。
このように、円高の場合は、海外旅行や海外留学にかかるお金が安くなったり、現地でたくさんお土産が買えたりします。
旅行に行くのが難しい場合は、気になる国のホテルやツアー、施設の入場料などの値段を調べてみると各国のお金の価値の違いを実感できるかもしれません。
日本円とアメリカドル、ユーロ、それぞれでいくらになるのか?など計算機を片手に調べてみるのもおすすめです。
企業の利益への影響
企業の利益にも大きな影響があります。日本には自動車や、半導体などを輸出してお金を稼いでいる企業が多くあります。円高と円安、どちらの方が輸出をしている企業にとって嬉しいでしょうか?
こちらも例を使って考えてみましょう。この場合は、日本の企業が輸出したものを買う人の気持ちになってみると考えやすいでしょう。なぜなら、輸出したものは日本円ではなく、海外のお金で買われるからです。
10,000円のものを輸出した場合、
- 1ドルが90円の時(円高):商品購入に必要なのは約111ドル
- 1ドル120円の時(円安):商品購入費必要なのは約83ドル
海外の人からしたら、83ドルで変える方がお得です。
すると、円安の時には日本のものは売れやすく、円高の時には輸出したものが売れにくくなります。
円高が続いて、日本のものが売れなくなると、日本の経済に影響が出てしまう可能性もあります。
円安と円高に関するよくある質問
Q1.円安とは何ですか?
円安とは、日本のお金「円」の価値が、外国のお金と比べて安くなることです。たとえば、以前は1ドル=100円だったのが、1ドル=150円になった場合、円の価値が下がって「円安」と呼ばれます。
Q2.円高になると、どんなことが起こりますか?
円高になると、外国からの輸入品が安く買えるようになります。たとえば、外国で作られた食べ物やおもちゃなどが、日本で安く売られるようになる可能性があります。また、海外旅行もしやすくなります。
Q3.円安になると、なぜ物の値段が上がるのですか?
円安になると、外国から買う物にたくさんの円が必要になるため、同じ商品でも値段が高くなってしまいます。そのため、ガソリンや輸入食品などの値段が上がりやすくなります。
Q4.円高になると、日本の会社にとっては困ることもあるのですか?
はい、円高になると、日本の会社が作った商品を外国で売るとき、値段が高くなってしまうため、売れにくくなる場合があります。その結果、会社の利益が減ってしまうこともあります。
Q5.どうして円安や円高になるのですか?
円安や円高は、円と外国のお金(ドルやユーロなど)を交換したい人の数や、国の経済の状態によって決まります。たとえば、日本の商品がよく売れているときは円を買いたい人が増え、円高になることがあります。
円安と円高はそれぞれにメリット・デメリットがある

円安と円高は、どちらが良いということはありません。どちらにも嬉しい場面と困る場面があります。その時の状況に影響されないためには、お金の価値は変わるものであると理解し、日々自分に合わせたお金の使い方ができるようにしていきましょう。
円安と円高は投資にも大きく関わっています。みらいいパークでは、投資の基本が学べるゲームも登場しています。小学生のうちからゲームで投資に触れて、少しずつお金に関する知識と経験を増やしていくのもおすすめです。
みらいいでは、お金に関する力を伸ばせるようサポートしています。お金に関する5つの力シリーズの記事はこちら!
使い方を知らなきゃ破産する?!子どもに伝えたい「お金を使う力」
小学生から始める!「お金を貯める力」の具体的な鍛え方
小学校では金融教育も始まっています。学校ではどのような金融教育がされているのか、こちらの記事で詳しく解説しています。
小学校の金融教育とは?実施されるようになった背景や家庭で取り組めることも紹介!

%20(1).jpg)





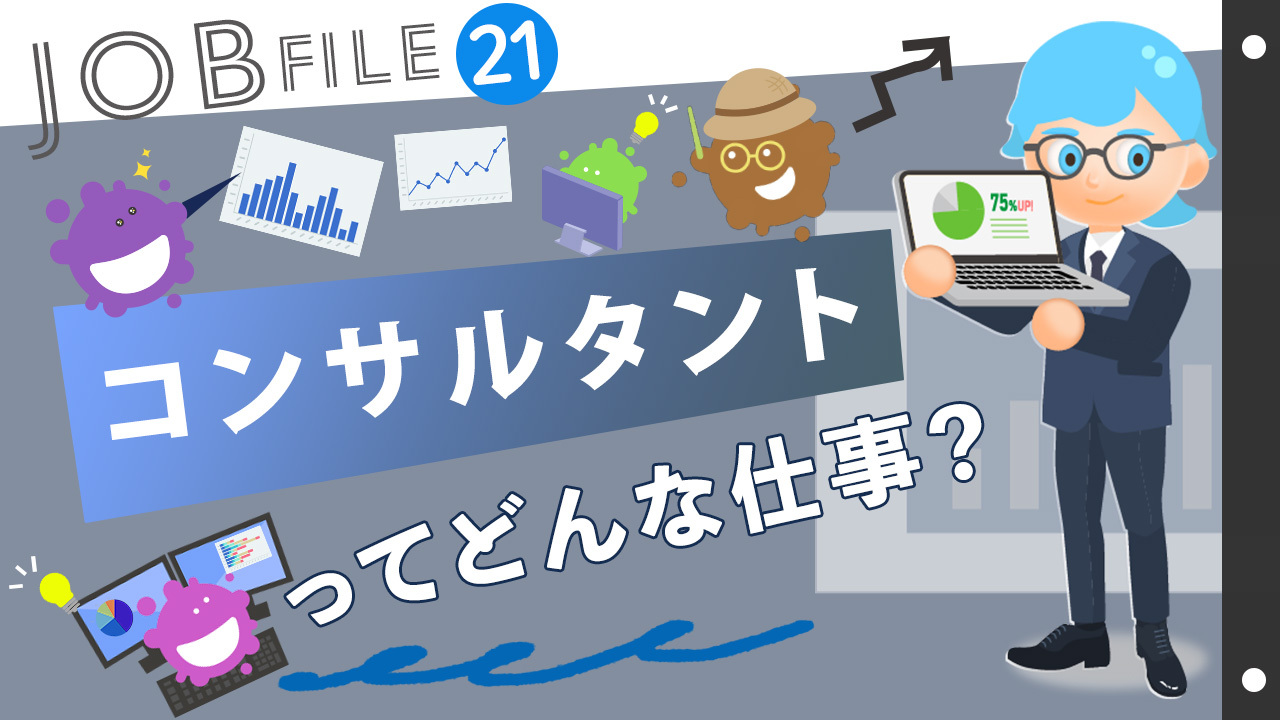
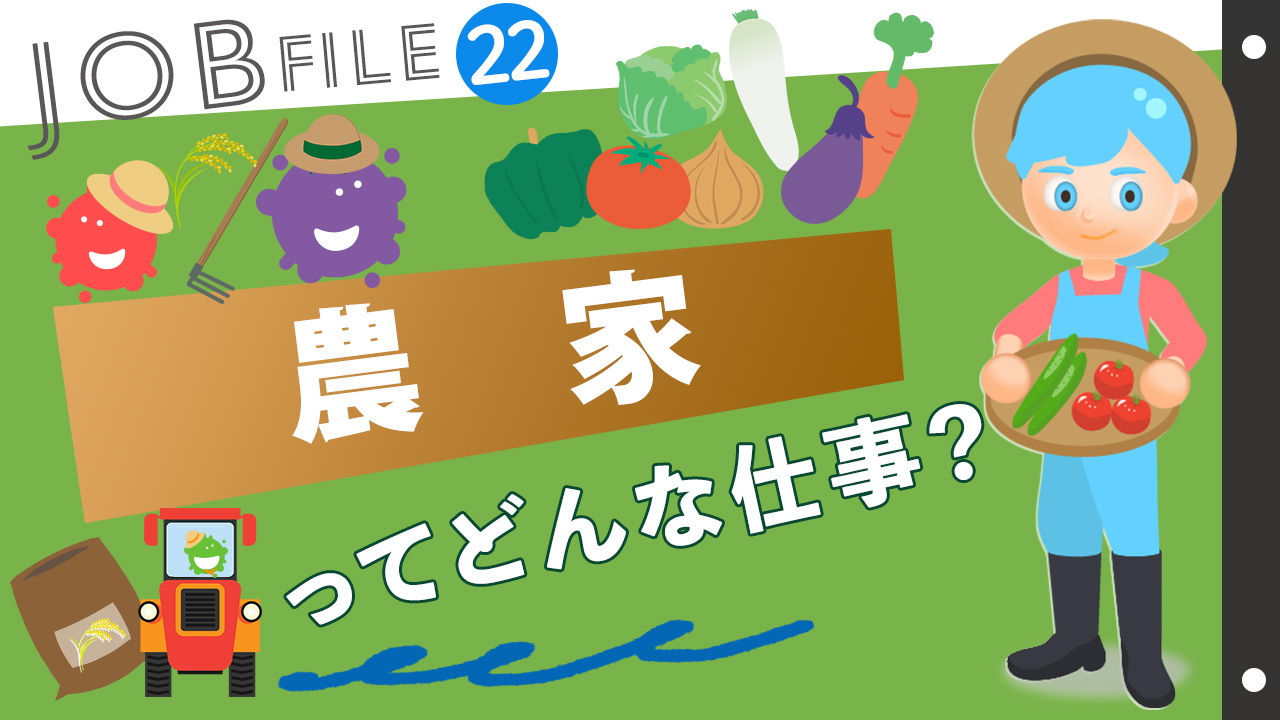
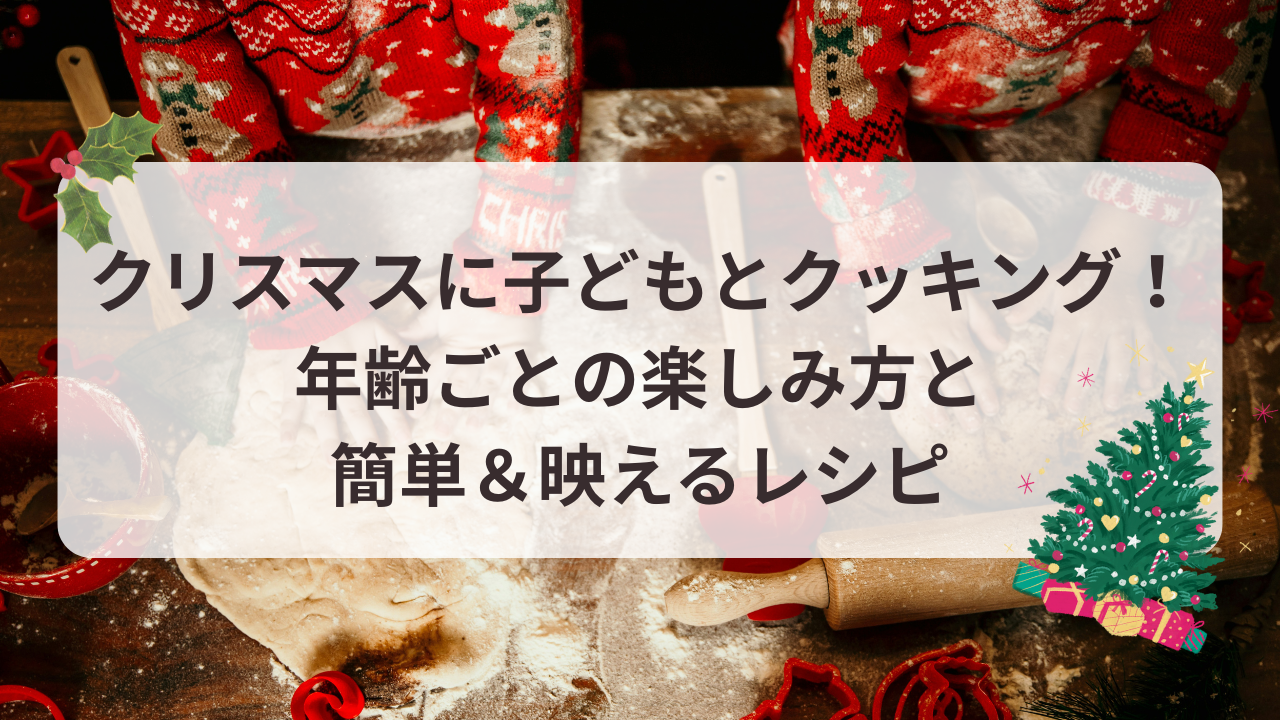
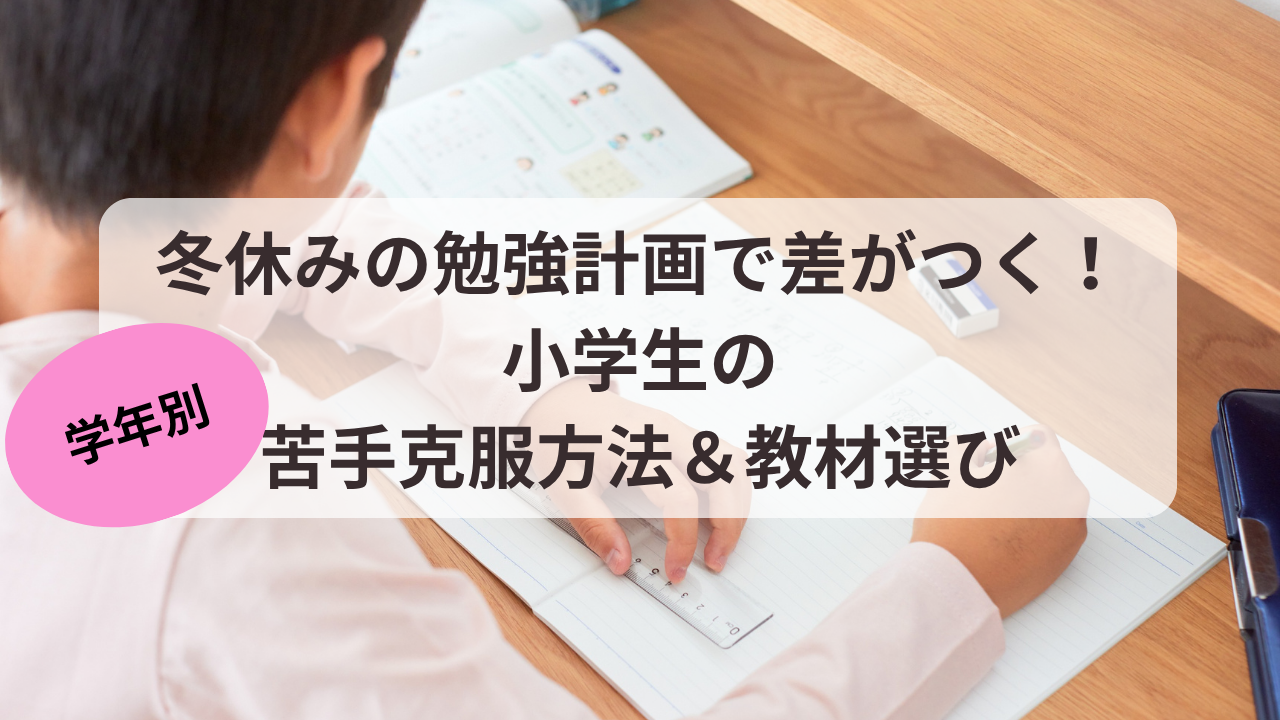

%20(1).jpg)